写真とビデオのデーター処理が間に合いませんので、とりあえず、文章のみの掲載です。---写真データーを追加します。ビデオのデーター処理が出来たら、ビデオから切り出した画像も掲載します。お御輿はビデオでしか撮影していませんので、ビデオデーター処理が出来てからの掲載になります。 ---サイト移転に伴い、ビデオデーター参照が出来なくなっています。現在、参照方法を検討中ですので、ご迷惑をお掛けしますが、しばらく、お待ち下さるようにお願い致します。 | |
 |
 |
 |
|
| 話が脱線しますが、少し、面白いことに気付きました。地図を見ていると、下方の周囲に台方という地名があります。下方と台方が複雑に入り組んでいるのです。分かったのは、下方は標高が低い位置にあり、台方は標高が高い位置にあることです。でも、その標高差はせいぜい10メートルから30メートル程度だろうと思います。印旛沼の水面と変わらない標高の場所が下方になっていて、それより高い位置が台方のようなのです。そして、街は、その標高差のある地形を上手に生かして形成されているらしいことも分かってきました。 印旛沼は、以前は、もっと大きくて、干拓されて、現在の大きさになったようです。干拓されたところは田圃になっています。干拓以前の沼岸付近には鳥居川岸というところがあり、現在でも鳥居があります。そして、その鳥居の近くに神楽殿があり、お祭りの時に獅子舞が舞われます。 脱線は、このくらいにして、お祭りの話に戻ります。麻賀多神社前でバスを降りると、早速、山車が目に入ります。山車の運行時間を聞いてみると、午後1時半からということです。まだ、8時45分くらいです。サイト管理者なりに調べたところでは、御輿と山車が連なって巡行するとあったので、午前中に山車も巡行すると判断していたのです。ところが、午前中に御輿が巡行し、午後になると山車の巡行が始まるということだったのです。う---ん、一石二丁とはならなかったか---と、正直、がっかりはしましたが、この時に、今日一日、麻賀多神社で過ごそうと決めたのです。午後から行く予定の飯田町と並木町のお祭りは来年にしようと思ったのです。こうなると、腰を据えてお祭りを楽しめる気分になってきたのです。 | |
 | |
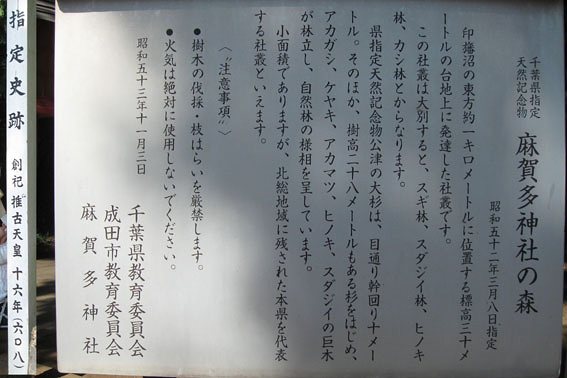 | |
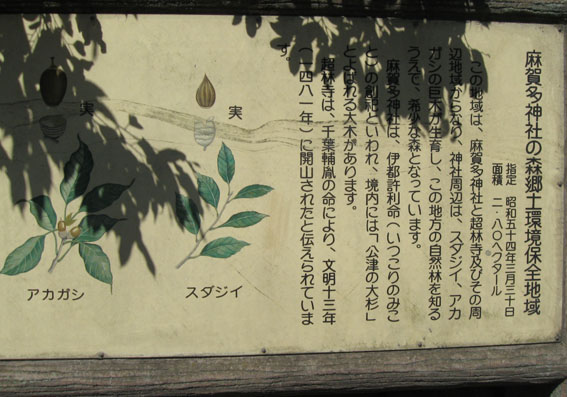 | |
 |
 |
 |
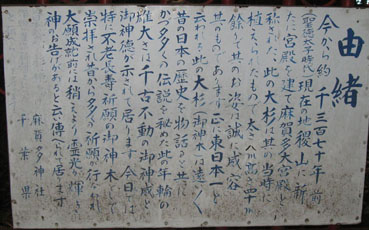 |
 |
 |
 |
|









